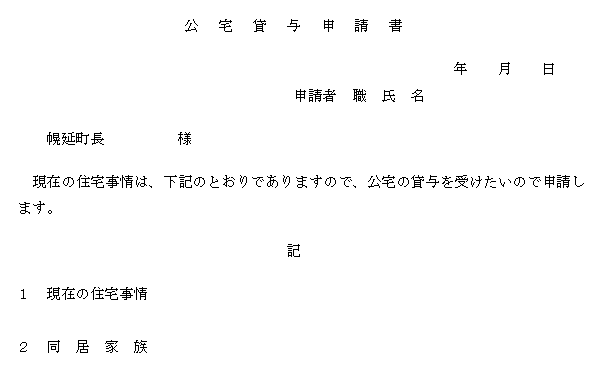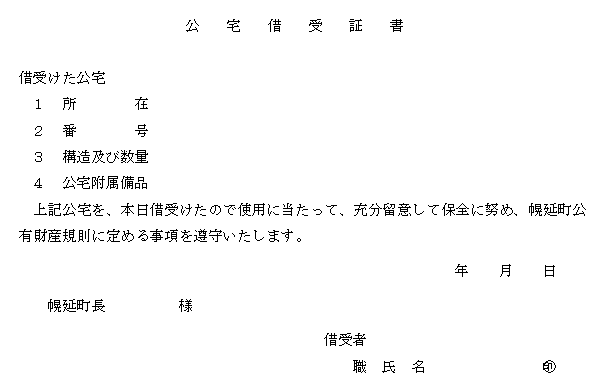第1条 町の所有に属する公有財産(以下「公有財産」という。)の取得、管理及び処分に関しては、法令及び条例に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
第2条 行政財産は、次の各号の種別によるものとし、当該財産の区別は当該各号に定めるところによる。
(1) 公用財産 町の事務若しくは事業の用に供し、又は供すると決定した行政財産
(2) 公共財産 町において直接公共の用に供し、又は供するものと決定した行政財産
2 普通財産は、次の各号の種別によるものとし、当該財産の区別は当該各号に定めるところによる。
(1) 第1種普通財産 公宅の用に供し、又は供することと決定した普通財産
(2) 第2種普通財産 第1種普通財産以外の普通財産
第3条 公有財産の取得、処分、管理並びに公有財産に関して生じた損害賠償の請求に関する事務は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者(以下「主務課長」という。)が行なうものとする。ただし、特に町長が必要と認めるときは、別に指定するところによる。
(1) 公用財産 当該公用の目的である事務又は事業を所管する課長。ただし、本庁舎の用に供するものを除く。
(2) 公共財産 当該公共の目的である事務又は事業を所管する課長
(3) 普通財産 当該財産に関する事務又は事業を所管する課長
第4条 学校その他直接教育の用に供する公有財産(以下「教育財産」という。)の管理及び処分に関する事務は、教育委員会に委任する。
第5条 町長又は教育委員会は、公有財産の引継をしようとするときは、次の事項を記載した書面により、これを引き受けるべき町長又は教育委員会に引き継がなければならない。この場合において、それぞれ所属の職員をして当該公有財産につきその確認をさせるものとする。
(1) 引継財産の表示(所在、区分、種別、名称、構造、数量、評定価格別)
2 町長が公有財産を取得した場合において、当該公有財産が教育財産であるとき、又は教育委員会の所管とすべきものであるときは、町長は、当該公有財産の引渡しに関し、必要な書類(図示を要するものであるときは、当該図面を含む。)を交付して、公有財産を教育委員会に引渡すものとする。この場合において、前項後段の規定を準用する。
3 前項の場合において、当該公有財産の引渡事務の処理は、総務課長が担当し、同項の書類の写を添えて、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
第6条 公有財産を異なる会計の間において、その所属の変更をし、又は所属を異にする会計をして使用させるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、当該公有財産を町において、直接公共の用に供する目的をもってこれをする場合又は町長が有償として整理することが不適当と認めた場合は、この限りでない。
第7条 公有財産を取得しようとする場合は、その目的物に私権の設定があり、又は特殊の義務が付されているときは、あらかじめこれを消滅させなければならない。
2 取得しようとする公有財産について、当該取得の原因となった契約、工事引渡し等に関する書類及び関係図面と照合して、適当であると認めたのちでなければ、その引渡しを受けてはならない。
3 不動産、船舶その他登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。
4 前項に掲げる公有財産については、法令に別段の定めがある場合を除くほか、その登記又は登録が完了したのちでなければ、代金の支払いをしてはならない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
第8条 主務課長は、その管理する公有財産の現況を把握し、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(2) 土地の境界が侵され、又は不明になっていないかどうか。
(4) 公有財産台帳の附属書面と符合するかどうか。
2 主務課長は、その管理する公有財産について、異動が生じたときは、総務課長に通知しなければならない。
第9条 総務課長は、公有財産を取得したとき及び前条第2項の規定による通知を受けたときは、次に掲げる事項を会計管理者に通知しなければならない。
(3) 取得した公有財産の見積金額又は評定価格及び算出基礎
2 前項の通知をする場合において、登記又は登録を要する公有財産に係るものについては、登記又は登録済であることを明らかにして行なわなければならない。
第10条 総務課長は、公有財産について、次に掲げる区分により公有財産台帳を調整し、必要な事項を明らかにしておかなければならない。
2 前項の公有財産台帳には、必要に応じ次に掲げる図面等を添付しなければならない。
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要があると認められるもの
3 総務課長は公有財産について異動(評価替も含む。)が生じたときは、その都度公有財産を整理しなければならない。
第11条 公有財産台帳に記載すべき価格は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額によらなければならない。
(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額
(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基く取得については、次に掲げる公有財産の区分に応じ、それぞれ当該に定める額とする。
(二) 建物及びその従物並びに船舶その他の動産及びその従物
建築又は製造に要した額(建築又は製造に要した額の算定が困難なものにあっては、評定価格)
その材積に単価を剰じて算定した額(材積を基準として算出することが、困難なものにあっては評定価格)
取得価格(取得価格によることが困難なものにあっては、評定価格)
第12条 主務課長は、公有財産について、3年ごとにその年の3月31日の現況について、別に定めるところにより評価しなければならない。
第13条 主務課長は、その管理に係る公有財産の用途を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により、町長の決定を受けなければならない。
第14条 主務課長は、公有財産の用途を廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により総務課長を経て、町長の決定を受けなければならない。
2 主務課長(総務課長を除く。)は、前項の規定により行政財産の用途の廃止について決定を受けたときは、当該行政財産に係る関係書類及び関係図面を添えて直ちに総務課長に引継がなければならない。
第15条 主務課長又は教育委員会は、当該管理又は所管の公有財産である土地と隣地との境界には、界標を立て常にその境界を明らかにしておかなければならない。
第16条 主務課長又は教育委員会は、当該管理又は所管する公有財産である建物には、名称を付しこれを表示しなければならない。
第17条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、
法第238条の4第4号の規定に基づきその用途又は目的を妨げない限度において、その使用を許可することができる。
(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。
(2) 公益に反しない範囲の講習会、講演会、研修会等の用に供するとき。
(3) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間その用に供するとき。
(4) 前3号以外のときで特に町長が必要と認めたとき。
2 主務課長は、第1項の規定により行政財産の使用の許可をするときは、許可を受けようとする者から次の各号に掲げる事項を記載した許可申請書を提出させなければならない。
(4) 前3号に掲げるもののほか主務課長が必要とした事項
3 第1項の規定による使用の期間は、同項第2号の場合にあっては10日、その他の場合にあっては1年を超えることができない。ただし、更新することを妨げない。
4 第1項の規定により許可する場合は、使用者、使用財産、使用目的、使用料、使用上の制限、使用許可の取消権、又は変更権の留保、使用財産の原状回復の義務、財産使用上の賠償の義務その他必要な条件を付することができる。
第18条 法第238条の2第2項の規定により教育委員会が教育財産の使用を許可する場合は、あらかじめ町長に協議しなければならない。
第19条 第1種普通財産の貸与を受けようとする者は、公宅貸与申請書(第1号様式)を提出しなければならない。
2 主務課長は、前項の規定により申請書の提出を受けたときは、町長の決裁を受け貸与を決定し、前項の財産の貸与を受けようとする者に通知し、貸与を受けた者(以下本条において「借受者」という。)より借受証書(第2号様式)を徴しなければならない。
3 総務課長は、現に貸与している公宅について居住替を必要とするときは、町長の決裁を受け決定し、現に貸与を受け居住している者に通知するものとし、通知を受けた者は10日以内に居住替をしなければならない。
4 借受者は、次に掲げる事項を厳守する外、常に必要な注意を払つて公宅及びその附属設備を正常な状態において維持しなければならない。
(1) 貸与を受けた公宅の原形を一切変更してはならない。
(2) 貸与を受けた公宅の一部又は全部を他に貸付けしてはならない。
5 公宅又はその附属施設が、滅失し損傷し又は汚損した場合において、町長がその滅失、損傷又は汚損が借受者の故意又は重大な過失により生じたものであると認めたときは、借受者は原形に復し、又はその費用を弁償しなければならない。
6 借受者は、次に掲げる事項に限り町長の許可を受けて自費建設することができる。ただし、これにより居住に支障を生ずることがないものであって、公宅の原形を変更しないこと及び明け渡しの際当該設置物を撤去し、又は町に寄附することを条件とするものでなければならない。
7 借受者は、次の各号のいずれかに該当したときには、1月以内に公宅を明け渡さなければならない。
(3) 第9項の規定により明け渡しを命じられたとき。
8 借受者が公宅を明け渡そうとするときは、町長に届け出てその指定した職員を立会の上検査を受けなければならない。
9 総務課長は、借受者の公宅の使用が当該公宅の管理上不適当と認めたときは、借受者に対し必要な指示を与え、なお借受者がその指示にしたがわないときは意見を付して町長の決裁を受け明け渡しを命ずることができる。
10 公宅の使用料は、町長が別に定める基準により毎月末日までに納付しなければならない。ただし、新たに公宅の貸与を受け、又はこれを明け渡した場合におけるその月分の使用料は、日割により計算した額とする。
第20条 第2種普通財産の貸付けを受けようとする者は、連帯保証人を立て(国又は地方公共団体が財産の貸付けを受けようとする場合は除く。)次に掲げる事項を記載した申込書を提出しなければならない。
2 主務課長は、前項の規定により申込書の提出があったときは、意見を付し契約書案を添えて町長の決裁を受けなければならない。
3 第2種普通財産を貸付ける場合は、契約書を作成しなければならない。ただし、極めて短期間の貸付けに係るものについては、この限りでない。
4 前3項の規定は、貸付契約を更新する場合に準用する。
5 第2種財産の借受者(以下本条において「借受者」という。)は、町長の承認を受けた場合を除くほか当該借受物件を他に転貸し、又はその権利を譲渡することができない。
6 借受者は、当該借受物件の用途の変更又は原形の変更をしようとするときは、文書により町長の承認を受けなければならない。
7 前項の規定により原形の変更の承認を受けた借受者は、返還の際原状に復さなければならない。
8 借受者は、天災その他の事故により借受物件に異状を生じたときは、速やかに町長にその旨を届けなければならない。
9 借受者は、借受物件を返還するときは、あらかじめ返還の時期(貸付期間満了前に返還しようとする場合に限る。)及び契約による返還の条件の履行について文書により町長に申し出なければならない。
10 借受者は、契約の条件に違反して借受物件の原形を変更し、又は故意若しくは過失により借受物件を荒廃させ、損傷し若しくは滅失したときは、その損害を賠償し、又は原状に回復しなければならない。
11 町長は、借受者が契約に違反したとき、又は公用若しくは公共の用に供するため必要と認めたときはいつでも契約の一部を変更又は解除することができるものとする。
13 第2種普通財産の貸付料(以下本条において「貸付料」という。)は、時価において町長が定め物価の変動その他の事情の変更により貸付料の額が時価に比し不相当となったときは、随時に改定するものとする。
14 貸付料は、次の各号に定めるところにより当該期日までに納入させるものとする。ただし、第1号の場合にあっては、前納することを妨げず、又は借受者が国若しくは地方公共団体の場合には契約で定める期日とすることができる。
(1) 1年以上の期間の貸付けに係るもの 毎年9月30日及び3月31日とする。
(2) 1年に充たない期間の貸付けに係るもの 契約で定める期日
15 貸付料は、年額をもって契約した場合は月割計算による額を単位とし、月額をもって契約した場合において1月に満たない期間の月があるときは、その月の分は日割計算によるものとする。ただし、耕作又は採草を目的とする貸付けについては、1年に満たない期間の貸付けであっても、年額を徴収する。
第21条 主務課長は、普通財産を売却し、又は譲渡(寄附を含む。)しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により、町長の決定を受けなければならない。
(3) 処分する普通財産の評定価格及びその算出価格
(5) 売却代金の延納の特約をするときは、その旨及びその内容
第22条 主務課長は、普通財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により、町長の決定を受けなければならない。
(2) 交換により提供する普通財産の表示及びその評定価格
(3) 交換により取得する財産の表示及びその評定価格
(4) 交換差金があるときは、その額及び納付の方法並びに延納の特約をするときはその旨及びその内容
(7) 交換により取得する財産の登記又は登録簿の謄本
第23条 主務課長は、前2条の規定により普通財産の処分及び交換をするときは、事前に総務課長に協議しなければならない。
(1) 当該普通財産の譲渡を受けたものが地方公共団体又は公共的団体であるとき 日歩2銭2厘
2 前項の場合において同項第3号の物件を除く物件については、抵当権を設定させるものとする。
3 主務課長は、担保物件の価格が減少したと認めるとき、又は担保物件が減少したときは、第1項各号に定める物件を、増担保又は代りの担保として提供させなければならない。
4 主務課長は、延納に係る売払代金又は交換差金が完納されたときは、担保を解除しなければならない。
第26条 主務課長は、
令第169条第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金の契約の特約をした場合において、次の各号のいずれかに該当するときは特約を解除しなければならない。
(1) 各年における延納に係る売払代金又は交換差金の納付金額と利息との合計額が当該財産の見積賃貸料の額に達しないとき。
(2) 当該普通財産の譲渡を受けた者の管理が適当でないと認められるとき。
2 前項の規定により延納の特約を取り消したときは、売払代金又は交換差金を一時に徴収しなければならない。
第27条 主務課長は、普通財産を処分(交換を含む。)したときは、次に掲げる事項を記載した書面により総務課長を経て会計管理者に報告しなければならない。
2 この規則施行の際、現に普通財産の貸与又は貸付けを受けている者は、第19条又は第20条の規定により貸与又は貸付けを受けたものとみなす。