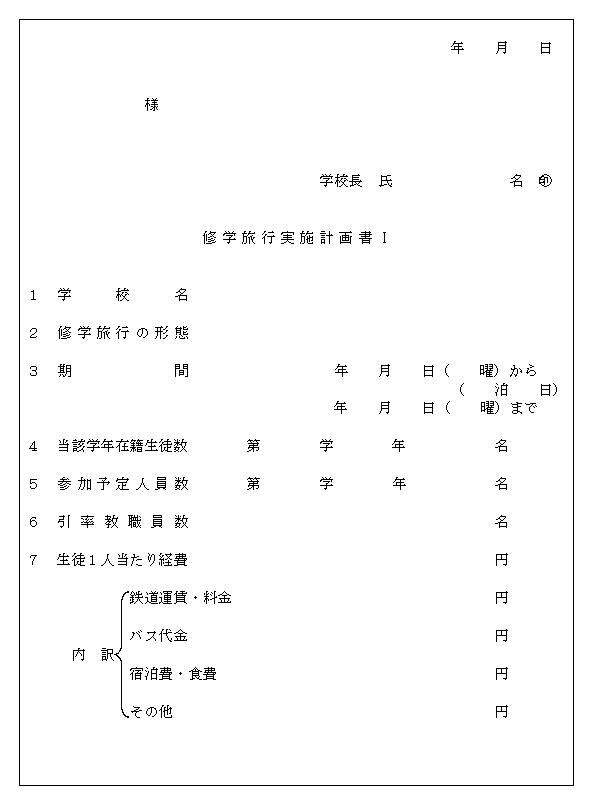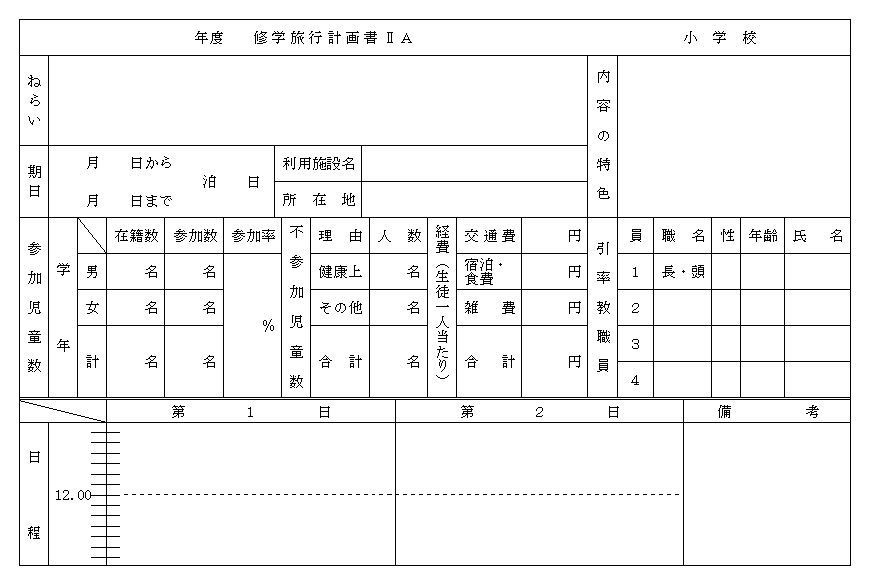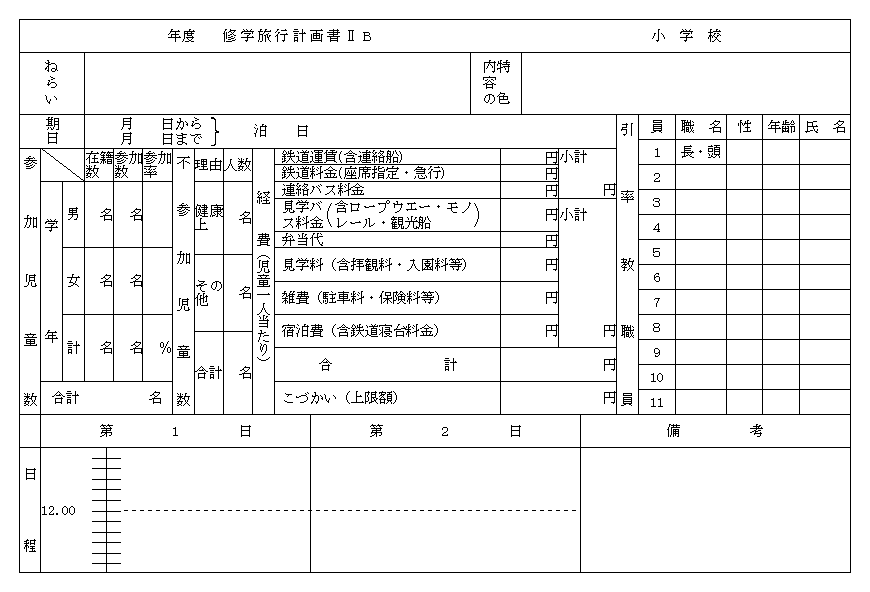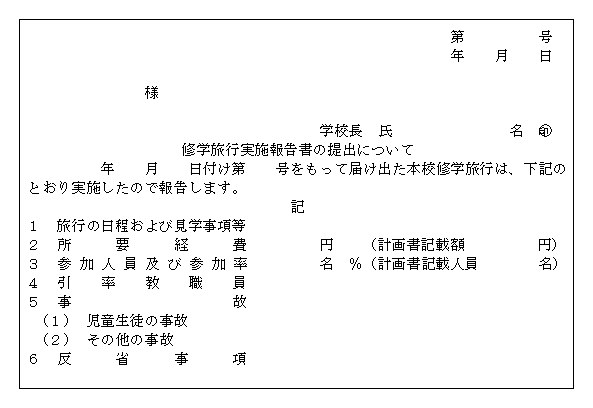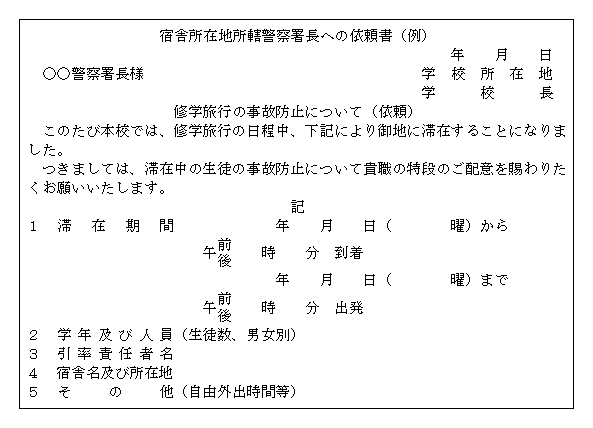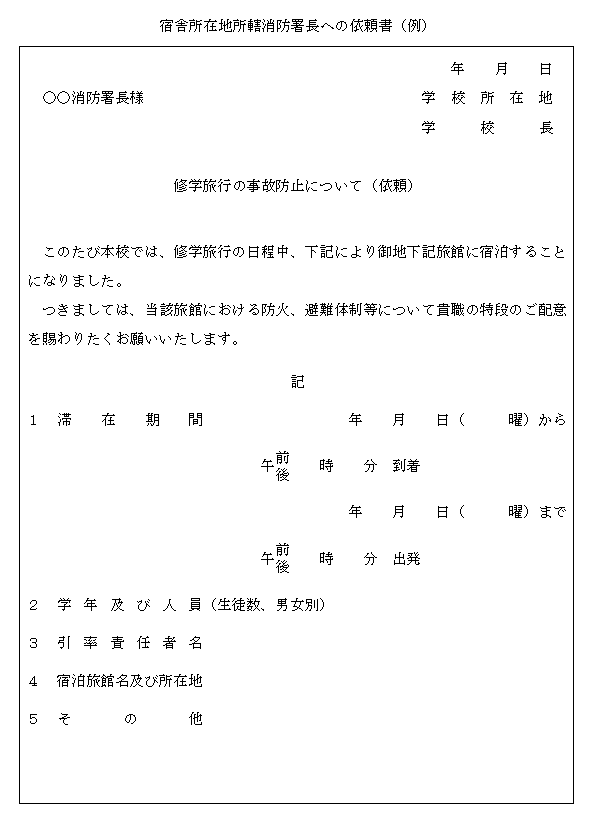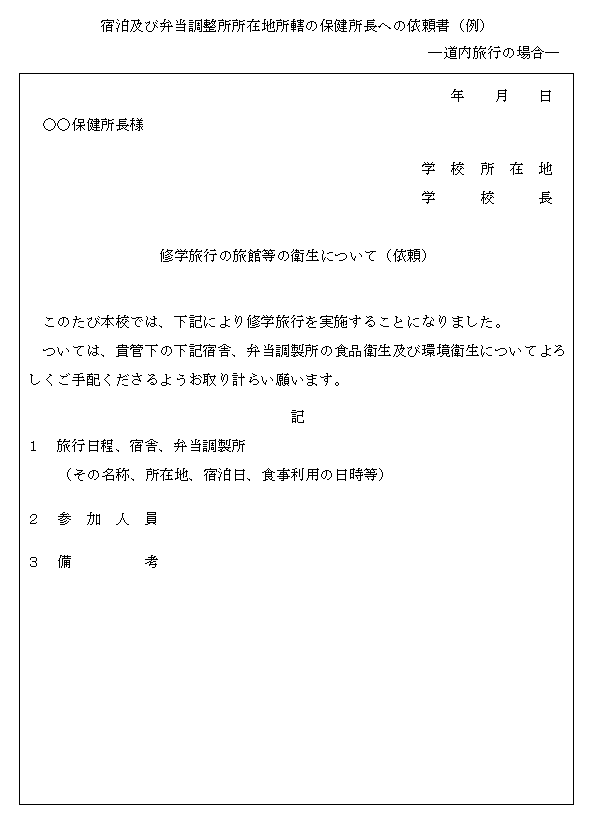�����G�Ǔ������w�Z�C�w���s���{��Ƃ��̗v��
���a45�N11���P������ψ���P�ߑ�Q��
���G�Ǔ������w�Z�C�w���s���{��Ƃ��̗v��
�C�w���s�́A�w�K�w���v�̂Ɏ�����Ă��鋳��ے��R�̈撆�̓��ʊ����Ɋ܂܂�A���̋���ے��̑S�̂����Ƃ����āA���̋��犈���ł͏\���ɒB�������Ȃ�����I���l���������邽�߂ɁA�������k�ɐ����S�̂̎w���Ǝ��H�ɏd�v�ȋ@��Ə��^������̂ł���B
���̌v��̎��{�ɓ������ẮA���̋���I�Ӌ`���A�\���������A�������k�̌��N���S�̂��߁A���S�̍���u������I���ʂ����߂�悤�����Ȕz�����Ȃ��ׂ��ł���B
�ړI�n�̑I��A�����̂��ݕ��A��ʋ@�ւ�h�����̑I��ɓ������ẮA�n��̎�����悭�͈����A���E���w�Z�Ԃ̘A���𖧂ɂ��A�������k�̐S�g�̔��B�i�K�Ɛ����o���̎��ԁA�����������猟���������A���ꂼ��̊w�K�Ώۂ��d�_�I�ɐ������A���ꂵ�A�\���Ȋ֘A���������čl���邱�Ƃ���ł���B
���̊�ƁA���̗v�̂́A��q�̂悤�ȈӐ}�̎����Ƌ���I���ʂ����߂悤�Ƃ������̂ł���B�e�w�Z�ɂ����ẮA���̎�|���\�����Ă��A���ꂼ��̎���ɉ����A�K�Ȍv����쐬���Ď��H����悤�z�����ꂽ���B
�C�w���s�̂˂炢���A�w�K�w���v�̂̎�|�����āA
(�Q)�@�w�K���e�̐[���g�[�A��̂���{��}��
��L�P�̂˂炢���\���B�������悤�A�n��̎��ԁA�w�Z�̓����y�ю������k�̔��B�i�K�ɉ�����ƂƂ��ɁA���E���E�����w�Z�̈�ѐ��ɗ����K�v���ŏ��̓����A�o��ɂ���čő�̌��ʂ������邽�߁A�C�w���s�̊�{�I�Ȍ`�Ԃ��A
�`�@�h���{�݁A�L�����v���̗��p�ɂ��h�����C�I�ȗv�f����Ƃ������
�a�@���n�ł̑̌��w�K��[�߂錩�w���s�I�ȗv�f����Ƃ�����̂ɕ����邱�ƁB
�Ȃ��A���{�̌v��ɓ������ẮA�e�Z��ʂɎ��̂��Ƃɗ��ӂ��邱�ƁB
�����o���̔�r�I�L���Ȏ����̑����w�Z�ɂ����ẮA��L�`�̌`�Ԃ��A�����o���̔�r�I�Ƃڂ��������̑����w�Z�ɂ����Ă͂a�̌`�Ԃ��ł��邾���������悤�v�悷����̂Ƃ��A�O�҂ɑ�����w�Z���a�ɂ��ꍇ�́A���A��̌v��ɂ��Ă��l��������̂Ƃ���B
���w�Z�ɂ�����C�w���s�̎��ԂƂ̊֘A���l�����āA�`�A�a�����ꂩ�ɏd�_�������悤�v�悷����̂Ƃ���B
�R�@�v��쐬��̋�̓I���ӎ����ɂ���
�C�w���s�̋�̓I�Ȍv��̍쐬�ɓ������ẮA�e�Z��ʂɎ��ɂ�邱�ƁB
�A�@�����́A�P���Q���ȓ��Ƃ���B�������A�ԑD���͔F�߂Ȃ��B
�C�@�́A�݊w���P��Ƃ��A�ŏI�w�N�Ɏ��{����B�������A���ʂ̎������ꍇ�́A���̌���łȂ��B
�E�@�o��́A1,500�~�ȓ��Ƃ���B�������A�S���Ȃ�тɈړ��E�A���̂��߂̃o�X�̉^���E�����͕ʂƂ���B
�A�@�����́A�R���S���ȓ��Ƃ���B�������A�ԑD���͔F�߂Ȃ��B
�C�@�́A�݊w���P��Ƃ��A�ŏI�w�N�Ɏ��{����B�������A���ʂ̎������ꍇ�́A���̌���łȂ��B
�E�@�o��́A3,500�~�ȓ��Ƃ���B�������A�S���Ȃ�тɈړ��E�A���̂��߂̃o�X�̉^���E�����͕ʂƂ���B
�w�Z�s���Ƃ��Ď��{���邱�Ƃɂ��݁A�S���Q���������Ƃ���B
�C�w���s�̎��{�v�揑����ѕ��̗l���A��o�̕��@���ɂ��ẮA�ʂɒ�߂�Ƃ���ɂ����̂Ƃ���B
���̎��{��́A���a46�N�S���P��������{����B
�i���j�@�����w�Z�ɂ��ẮA���������w�Z�ɏ�������̂Ƃ���B
�C�w���s���v�悷��ɓ������ẮA�܂����Z�̎������k�̔��B�i�K�A�w�Z�̓����n��̎��ԓ��ɑ����āA�˂炢�m�ɂ���K�v������B
�e�w�Z���v�悷��ۂ̎w�j�ƂȂ�悤��{�I�ȁu�˂炢�v�����̂悤�ɐݒ肵���B
����̐����̏���͂Ȃꂽ�p���I�Ȑ����̒��ŁA���F�A���t�Ƃ̒����Ԃɂ킽��l�ԓI�ȐG�ꍇ����A�K������W�c�I�s�������邱�Ƃɂ���āA�l�i�̒��a���锭�B�ƎЉ�I�A�ъ����琬����B
(�Q)�@�w�K���e�̐[���g�[�A��̂���{��}��
���R�A�����A�o�ρA�Y�ƁA�������Ɋւ��関�m�̐��E�ږK��邱�Ƃɂ���āA�����̎����⌻�ۂ��w�K�o���ɉ����Đ��������������A�Ȋw�I�ɍl�@����ԓx��L���ȏ���琬����B
�e�w�Z�ɂ����ẮA�����̊�{�I�Ȃ˂炢���ӂ܂��āA���Z�̂˂炢����̓I���d�_�I�ɖ��m�ɐݒ肷��ƂƂ��ɁA�������k�̎�̓I�Ȋw�K�Q���𑣐i���A�ړI�̒B���ɓw�߂邱�Ƃ��̗v�ł���B
�n��̎��ԁA�w�Z�̓����y�ю������k�̔��B�i�K�ɉ�����Ƌ��ɏ��E���E�����w�Z�̈�ѐ��ɗ����K�v���ŏ��̓����A�o��ɂ���āA�ő�̌��ʂ������邽�ߏC�w���s�̊�{�I�`�Ԃ����̂悤�ɒ�߂�B
�i�`�j�@�h���{�݁A�L�����v���̗��p�ɂ��h�����C�I�ȗv�f����Ƃ������
�i�a�j�@���n�ł̑̌��w�K��[�߂錩�w���s�I�ȗv�f����Ƃ������
�Ȃ��A���{�̌v��ɓ������ẮA�e�w�Z��ʂŎ��̓_�ɗ��ӂ��邱�ƁB
�`�̌`�ԂŎ��{����w�Z�́A�����o���̔�r�I�L���Ȏ����̑����w�Z�ł����A
�a�̌`�ԂŎ��{����w�Z�́A�����o���̔�r�I�Ƃڂ��������̑����w�Z�ł���Ԃ��ƂɂȂ�B
���G�Ǔ��ɂ����ẮA�����̐����o���g�[�̈Ӗ�����A�����̊ԁA�a�̌`�Ԃ���ƂȂ낤���A�n��A�w�Z�̕K�v�ɉ����āA�`�̌`�Ԃ��Ƃ邱�Ƃ������Ă��悢�B
���w�Z�ɂ�����C�w���s�̎��ԂƂ̊֘A���l�����āA�`����A�a���]�܂��́A�a����A�`���]�Ƃ���悤�v�悷����̂Ƃ���B
�v��́A�Z�����ӔC�������č쐬������̂ŁA�S�Z�I�Ȍ����g�D������A��ɉ��P��S�����A�K���Ȗ��Ȏw���v������ĂȂ���Ȃ�Ȃ��B
���̂��Ƃɂ��ẮA�����܂ł��w�Z�Ƃ��Ă̎�̐����������Ȃ���Ȃ�Ȃ����A�K�ȕ��@�ɂ����Ď������k���v�旧�ĂɎQ�������邱�Ƃ́A�w�K�ӗ~�����߁A����I�����𑣐i���邤���Ɍ��ʂ�����̂Ŕz�����邱�Ƃ���ł���B
�Ȃ��A�������k�̎Q���ɂ��ẮA�S���Q���������Ƃ��A����ɂ���ĕs�Q���҂̂���ꍇ�ł����̎Q�����́A�����̂W���ȏ�Ƃ���B
���{��ɂ����鎞���A�����A�A�o��y�ї��s�͈̔͂́A���̌��x���������̂ł���̂œ��ɗ��ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������A�s�֒n�ɂ��邽�߁A����ɂ�肪�����ꍇ�́A���炩���ߋ��璷�Ƌ��c���邱�Ƃ��K�v�ł���B
���{�̎����ɂ��ẮA�Z���s���A�C������A���s�n�̎��R�I�Љ�I���������\���l�����A�Ȃ�ׂ���ʗ��q�̍��G���鎞���͔�����悤�ɂ��邱�Ƃ��]�܂����B
�i�q�𗘗p����ꍇ�́A�c�̎���̌��肪���{�̂T�����O�ł��邽�߁A�N�x�����̌v��ɋ������邱�Ƃ̂Ȃ��悤�\�����ӂ��邱�Ƃ��K�v�ł���B
�Ȃ��A���s���Ԓ��ɏj�����܂ނ��Ƃ͂ł��Ȃ��B�w�N�n�x�Ɠ��y�ъw�N���x�Ɠ����Ԃ��܂ނ��Ƃ��K���łȂ��B
���w�Z�̓����́A�P���Q���ȓ��Ƃ���B�������A�ԑD���͔F�߂Ȃ��B
���w�Z�̓����́A�R���S���ȓ��Ƃ���B�������A�ԑD���͔F�߂Ȃ��B
�݊w���P��Ƃ��A�ŏI�w�N�Ɏ��{����B�������A���{�w�N�ɂ��Ă͕����A���X���̊w�Z�y�ѓ��p�����̓��ʂ̗��R��L����ꍇ�́A���̌���łȂ��B
�o��ɂ��ẮA�ł��邾���ی�҂̕��S���ߏd�ɂȂ�Ȃ��悤�A�X�Ɉꎞ�ɑ��z�o���v���邱�Ƃ̂Ȃ��悤�ϗ��Ăɂ��A�����ɂ킽���ď�������悤�l�����ׂ��ł���B
���v�o��́A���{�N�x���ɋ���ψ���e�w�Z�ƒ������肷��B
���w�Z�̌o���1,500�~�ȓ��Ƃ���B
���w�Z�̌o���3,500�~�ȓ��Ƃ���B
�o��Ɋ܂܂����̂́A�h����A�H��A���w�o�X����A�q�ϗ��A�����i�فj���A�G��A���̒��ɂ́A�S���̉^���y�ї����i�}�s���A���Ȏw�藿�j�w�Z�Ɖw�A�w�Əh�ɂ����ԃo�X����͊܂܂Ȃ��B
�S�s����ݐ�o�X�ɂ��ꍇ�́A�o�X����̑��z����w�Z�Əh�ɂ����ԍŒZ�R�[�X����Ԃ����ꍇ�̑���������������z�����w�o�X����Ƃ݂Ȃ��B
���{�ɓ������ẮA���炩���ߎ��̊e���ɂ��Ă��_�������Ă����B
�C�@�ً}���Ԕ����̍ۂ̉��}�[�u�A�A�����@�y�т��̂��߂̑g�D�̐�
�E�@�؍ݒn�o�H�ɂ����铹�H���ʂ̏y�ѓ`���a�A���s�����`���̔����̗L��
���@�w�K���e�̐��I�ƍs�����Ԃ̓K����
�h�����C���e�〈�w�n���w�ΏۂI���A�w�K�s�����Ԃ̓K�����ɗ��ӂ���ƂƂ��ɁA���{���ԑS�̂�ʂ��Ă�Ƃ�̂�������ƂȂ�悤�v�悷��B
���ɁA�������Ԃ̊m�ۂɗ��ӂ��A��������[��ɂ���ԗ��s�v��͔����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̂��ߌߑO�W���ȑO�y�ьߌ�U���Ȍ�ɂ�����S�̓I�ȏW�c�����́A���W�I�̑��̎��{�����ʂ̏ꍇ�������Ă͍s��Ȃ��悤�ɂ��邱�Ƃ��]�܂����B
�Ȃ��A��ʕs�ւȒn��ɂ����Ă�ނ��o���������ɂȂ薔�͋A���������������Ƃ��͎��O�ɋ��璷�̎w������B
�܂��A�������o�X�𗘗p����ꍇ�́A�A�����s���Ԃ��ő���Q����30���Ƃ��A20���ȏ�̋x�e���Ԃ�K���݂���ƂƂ��ɂP���̎����s���Ԃ��U���Ԉȓ��ɂƂǂ߂�悤���ӂ���B
���@���s�͈̔́i���s��y�эs���j
���s�n�̑I��ɂ��ẮA�������k�̋���I���ʂ����Ƃ��A���̐S�g�̔��B�ɑ�����悤�w�K���e�A���O�w���A�ی��A��ʎ���A�����A��J�x�A�댯���ɂ��ď\���������A����A�������k�ƂƂ��ɋ��c���肵�A��������ɒm���x�ɘf�킳��邱�ƂȂ��A�ł��邾�����O�ɒ���������A�ڍׂȎ����͂���Ȃǂ��āA�w�K�K�n�Ƃ��Ẳ��l���f�ɗ����đI�肷��B
���ɁA������ό��n��I�肷��ꍇ�ɂ��ẮA��ʂɊw�K�������L�x�ł��锽�ʁA���y�I�ӂ�͋C�����̂������̂ŏh�ɂ�s�����Ԍ��w�Ώۓ������肷��ۂ͍אS�̒��ӂ��͂炢�D�܂����Ȃ�������^���邱�Ƃ̂Ȃ��悤�ɂ���B
�s���ɂ��ẮA���E���w�Z�̌v�悪�d�����Ȃ��悤���݂̘A�����c�ɂ���Ă����ނˎ��̂悤�ȃR�[�X��I�Ԃ悤�ɂ���B
�@�@���w�Z�@���G�Ǔ��y�ыߐڒn�A�j�ՁA�Љ�A�Y�ƁA���R���C�w���s�̖ړI�B���ɂӂ��킵���Ƃ�����d�_�I�ɐ��I����悤���ɗ��ӂ���B
�A�@���w�Z�@�����ɂ�����j�ՁA�Љ�A�Y�ƁA���R���C�w���s�̖ړI�B���ɂӂ��킵���Ƃ�����d�_�I�ɐ��I����悤���ɗ��ӂ���B
|
|
�R�[�X | ���w�ꏊ |
���G | �@ |
��� | �@ |
�]�� | �@ |
�D�y | ��ʌ����A�Ύ��A�e���r�� |
������ | �����ٌ��w�A�`�p�s�s |
��R�k | ���������i����A��A���d���j |
�D�y | �s���A�f�p�[�g�A�������A�A�����A�c�����A�����A���A�t�����A��w�A�V���� |
��� | �@ |
���G | �@ |
|
|
���G | �@ |
�[�� | �Ύ��A�_���Â��� |
���� | �s���A���a�ʂ�A�m�g�j�A���N�Ȋw�فA��Ռ����A�ыƎ������A�����A�����فA������ |
�w�_�� | ���������A�i����ߗ��j�A����A�����E��͂̑ꓙ�A�Ζk�� |
���� | ����������肤�ǂ� |
�_������ | �@ |
���G | �@ |
�`�̌`�ԂŎ��{����w�Z�ɂ����ẮA�h�����C�̌��ʂ����߂�悤�h���n�A�h�ɓ��\���������������ŁA�w�K�K�n��I�肵�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
|
|
|
�R�[�X | ���w | ���C |
���G �i�ԑ����w�j | �������d���A�S���A��h�A�z�R�s�s�A�Ύ��A�Ύ땽�� | �@ |
�D�y | �@ | �@ |
��� | ���`�A�E������ | �@ |
�Ϗ��q | �Ϗ��q�`�A���q���� | �@ |
�o�ʉ���n | �n�����J�@����s�s�A���A�N�b�^���A�P�[�u���A���ʂ܁A������ | �@ |
����� | �H�Ɠs�s�A�d�H�ƁA�f�Ս`�A�����فA�n���݂��� | �@ |
�Ƃ���� | �Ƃ���A���a�V�R�A�Ώ�V���A�ΎR�n�сA�J���f���A�X�є����فA�M�ѐA�����A�L��x | �@ |
�͂��� | �@ | ���َs�����w�Z�Ƃ̌����� |
�܂�傤�s�A�g���s�X�g�A�����ؔ�A���A���D�A�`�p�s�s�A���Ɠs�s�A���َR�A���҂݂����A�k�m���� | �@ |
�i�ԑ����w�j | ��������A���܂��x�A�r�Ă��R�A�ӂ�Θp�̋��ƁA�ΎR�n�сA�ΎR�D | �@ |
�D�y | �@ | �@ |
���G | �@ | �@ |
|
|
|
�R�[�X | ���w | ���C |
���G | �@ | �@ |
�D�y | �@ | �@ |
���R���A���a�V�R�A�M�ѐA���� | �@ |
�Ƃ���� | �Ώ�V���A�X�є����� | �@ |
����� | �����فA�V���{���� | �@ |
�x���� | �x���� | �h�����C�A�o�R�̑O��w�K����O�R�o�R |
�D�y | �s�����w�i����R�A�������j | �@ |
���G | �@ | �@ |
|
|
|
�R�[�X | ���w | ���C |
���G | �@ | �@ |
������ | �_���Â���A�w�_���A����ߗ��A����A�����A�Ζk���A����s�X�A��� | �@ |
�ԑ� | �V�s�R�A�����ԉ��A�Ƃ����A���y���A���ΘH�A�a�Ք����A���� | �@ |
���y | �쓒����A�����R�A�͂����A������ | �@ |
��q�� | �����A�}�����A�|�b�P�A�Ώ�V���A�Y�������x | ��q���������w�Z�Ƃ̌����� |
���� | �����сA�A�J�G�]���A�����ь����� | �@ |
�ʂ��� | �l���A�G�������Y�n�� | �@ |
�эL | �돟�� | �@ |
�����H | �`�p�W�]�A�����ؔ�A�t�̌A | �@ |
�эL | ��������A���傤�� | �@ |
���G | �@ | �@ |
��L�̗�́A�a����A�`���]�őg�܂ꂽ���̂ł���B���̂悤�Ɍ��K�I�v�f��g�݂��܂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̏ꍇ�A���w���e�I����Ȃǂ�Ƃ�̂�������ƂȂ�悤�g�݂����邱�Ƃ��K�v�ł���B���K�̑g�݂��݂ɂ��ẮA���ɓo�R�A������n�ӂ�����H���݂���Ɏ����Ă��邪�A����e�w�Z�̈�w�̌������]�܂��B
�Ȃ��A�`����E�a���]�Ƃ��Ď��H����w�Z�ɂ����ẮA���e�̏[���ƌ������ʂ����߂���h���n�A�h�ɓ������イ�Ԃ����������Ŋw�K�K�n��I�肵�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
(�P)�@�Z���́A�������E�������肷��ɓ������ẮA�T�d�ɂ�����s���ƂƂ��ɍZ�����͋����Ⴕ���͂���ɂ����҂������҂Ƃ���B�܂��A�Ȃ�ׂ��{�싳�@����������A���q���E�����܂߂�悤�w�߂�B
�����ӔC�҂́A������̑S�ӔC���ƂƂ��Ɉ����҂̎w���g�D�⎖�����S�m�ɂ��āA��������i�ߖ��S�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
(�Q)�@�����҂̗��s���ɂ�����Ζ��ɂ��ẮA���炩���ߋΖ����Ԃ̊���U���K�ɂ���ȂǐT�d�Ȕz�������Ă����˂Ȃ�Ȃ��B
�C�w���s���{�ɓ������čZ���́A���̏��ނ����̎����Ƃ���ɂ�肻�ꂼ��R���쐬���A�s�������璷�ɂQ����o���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�ʋL�l���P�ɂ��쐬���A���N�x���������܂łɒ�o���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
���w�Z�ɂ����Ă`�̌`�Ԃɂ��C�w���s�ɂ����Ă�
�ʋL�l���Q�ɂ��v�揑�U�`���A�a�̌`�Ԃɂ��C�w���s�ɂ����Ă�
�ʋL�l���R�ɂ��v�揑�U�a���쐬���A���{�̂R�����O�܂łɒ�o���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
���w�Z�̏C�w���s�ɂ����ẮA
�ʋL�l���S�ɂ��v�揑�V���쐬���A���{�̂R�����O�܂łɒ�o���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�ʋL�l���T�ɂ��쐬���A�C�w���s�I����Q�T�Ԉȓ��ɒ�o���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
��L�̗l���́A���G�Ǔ����E���w�Z�C�w���s���{��Ƃ��̗v�̂��������̂ł���B
(�Q)�@�C�w���s�̈��S�m�ۂɂ���
�Z���́A�C�w���s���̎��̂𖢑R�ɖh�~���邽�߁A���̏��ނ��쐬���A���{�̂Q�T�ԑO�܂łɁA���ꂼ��̋@�ւ̒��ɑ��t���邱�Ƃ��]�܂����B
�A�@�h�ɏ��ݒn�����̌x�@�����ւ̈˗����i
�ʋL�l���U�j
�C�@�h�ɏ��ݒn�����̏��h�����ւ̈˗����i
�ʋL�l���V�j
�E�@�h�ɋy�ѕٓ����������ݒn�̕ی������ւ̈˗����i
�ʋL�l���W�j
�������k�̎����I�Ȉӗ~�����҂���A�w���̂�����ɂ���ẮA����߂đ傫�Ȑ��ʂ���������̂ł��邩��A�e�w�Z�ɂ����Ă͎��O�ɏڍׂȎw���v����쐬���āA�C�w���s�̂˂炢����e���ɂ��ē��ݎ��Ԃ�݂��A�\��������[�߁A�ϋɓI�Ɋw�K�Ɏ��g�܂���K�v������B���̏ꍇ�K�Ȏw���̂��ƂɎ���I�ȃe�[�}�̐ݒ�ǂ̕Ґ������s�킹�邱�Ƃ��]�܂����B
���w����h�ɖ��͎ԑD���ɂ����ẮA�������⋦�����̂���s�����d�v�ł��邱�Ƃ𗝉������A�K���̏���⎞�Ԃ̗�s�A�@�q�ȍs���A�ǂ̃`�[�����[�N������������A���R����╶�����ی�Ȃǂ̑ԓx�̈琬��}��ׂ��ł���B
�܂��A���O��������邱�Ƃɂ���āA�y�������s�ƂȂ邱�Ƃ����̎w���Ƃ̊֘A�ɂ����Ă��炩���ߓO�ꂵ�Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
���s���ɔ��a�҂�������ƁA�{�l�͂������A�S�̍s���ɂ��e�����y�ڂ��₷�����Ƃ𗝉������A���s���̌��N�Ǘ��ɂ��ẮA����אS�̒��ӂ��悤�w������ƂƂ��ɁA�w�Z�Ƃ��Ă͏o�������O�ɎQ���ґS���̌��N�f�f�⌒�N�������s������A���ɕK�v�ƍl������҂ɂ��Ă͕ی�҂���a����a�C�̌X���������������Ă������̑[�u���u���邱�Ƃ��K�v�ł���B
���s���́A�������k�̐����s���A�S�g�̔�J�A���S�A������A�D��S�A�Q�W�S���Ȃǂ��玖�̂��s�̋N���邱�Ƃ������̂ŁA�����𖢑R�ɖh�~���邽�߁A���̊e�������܂߂ēK�Ȏw�����s���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�A�@���߂�ꂽ�������ԓ��ɂ����āA�\���������Ƃ�悤�S����������B
�C�@���p����{�ݐݔ��̐ӔC�ғ�������S����m�F����ƂƂ��ɁA�������k�ɂ����̂��Ƃ����m������B
�E�@��ʋK�������炳���A���ɕ��s���ɂ͎Ԃ̓����ɒ��ӂ�����B
�G�@�o�X�A�ό��D�̗��p�ɂ��Ă͈��S���Ƃ��A����ȏ�̗��p���~�߂�����ƂƂ��Ɏ������k�ɑ��Ă͌W���̎w���ɏ]���悤�w�����Ă����B
�I�@�댯�Ȓn��␅��ڋ߂��邱�Ƃ����ɋ֎~����B
�J�@�����A�i���A���K����̔�s�ɂ͂���Ȃ��悤���߂��܂��Ȏw�����s���B
�L�@���R�s�����ɂ́A�ǒP�ʂōs�������A�ЂƂ肠�邫�͌��ɋ֎~����B
�N�@�˔��I�Ɏ��̂����������ꍇ�ɂƂ�ׂ��S���܂���ޔ��A�~��A�A�����̑[�u�ɂ��āA�˂ɏ\�����������Ă����B
������g�s�i�͂ł��邾���ȑf���|�Ƃ��A�V�����T���A�ߗނɂ��Ă��ؔ��Ȃ��̂������ƂƂ��ɐn�����̊댯���͌g�s���Ȃ��悤�w������B
(�U)�@���Â����̐����Ǝx�o�̎w��
���Â����̎x�o�z��z�肵�āA���̏���z���ł��邾�������A����������Ď��Q�����Ȃ��悤�ی�҂Ƃ��\���A�����Ƃ�ƂƂ��ɂ��̎x�o�ɂ��Ă��w������B
�V�@���s���̑[�u�A�w���ɂ���
�����҂́A�����ӔC�҂𒆐S�Ƃ��āA��ɘA�����Ƃ荇���������A��͂��s���������k�̐S����Ԃ�s�����������Ă������Ƃ�����߂đ�ł���B
�W���A���U���͂������A�A�Q�A�N�����~�ԑD�̍ۂɂ͐l���̓_�Ă��s���ƂƂ��ɏ�Ɉُ�̗L�����m�F���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�����ӔC�҂͏���I�m�ɔ��f���A�\�����Ȃ�����̕ω��ɍۂ��ẮA�����A�o�H�A���w���ύX������A�w�Z���̑��W�@�ււ̕�����ȂǗՋ@���ς̑[�u���u����B
�������k�Ƃ̖]�܂����l�ԊW�̕ێ�����w�������ʓI�ɂ����߂闧�ꂩ��N���A�H�����̍s�����Ƃ��ɂ���悤�S������B�܂������҂̍s���́A�w�Z�ɂ���Ƃ������������k�ɗ^����e�����傫���̂Ŏ��琂�͂ɓw�߂ċ��t�̕i�ʂ�M���������Ȃ��悤�ȍs���͌��ɂ��ށB
����ɁA�����҂́A���t�Ƃ��Ă̎��o�ƈ���������������k�ƍs�����Ƃ��ɂ��钆�Ő��k�����̂悢�@��ƂȂ�悤�z�����Đڂ���B
�������A���ꎙ�����k�Ɍ�����s�����F�߂�ꂽ�ꍇ�́A���ɑS�̂ւ̉e���◷�s��ł̕s�ˎ��ł��邱�ƂȂǂ��l���A�K�Ȕ��f�ƁA���R����ԓx�ɂ���āA������w�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�������k�̖\���\�H�A�����s���A�˂т��A���s�����`�A��J�ߏd�Ȃǂɒ��ӂ��āA���N���������A��ɓK�Ȏw����������B
�h�ɂł́A�݂���ɁA�͂��������邱�ƂȂ����ɖ�͐Ïl��ۂ悤�S����������B
�܂��A�[�H��ɂ͎��Ԃ���݂��Ĕǂ��Ƃɓ����̊w�K��s���̔��ȁA�܂Ƃ߂��s���悤�w������B
�Ȃ��A�������A�̂������A�함�̔j���⎝���o���A���̑��̂�������s�ׂ̂Ȃ��悤���d�ɒ��ӂ��Ă����B
����ɁA�h�ɂɂ����āA���Z���Ɠ��h����ꍇ�ɂ́A�����ӔC�҂͐���̈����ӔC�҂ƘA���𖧂ɂ��Ė��p�̖��C�̐����邱�Ƃ̂Ȃ��悤�z������B�Ȃ��A�h�ɓ�����́A�������m�F���������k�Ɏ��m�O�ꂳ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
���w����ԑD���A�h�ɂł̒j���̌��ۂ͖��邭���S�Ȃ��̂ƂȂ�悤�K�ɔz������B���ɒ��w���ɂ��Ă͕����Ō��ۂ����݂Ɉِ��𗝉��������悤�w�����邱�Ƃ��]�܂����B
���{��ł��邾�������@��ɔ��ȉ�������������k�̗��s���̊w�K��s���ɂ��čl��������ƂƂ��ɁA�����҂����ȉ�������ė��N�x�̏C�w���s�v��̉��P�Ɏ�����B
�w�K�����A�����ۑ�A���z�Ȃǂ��܂Ƃ߂����A�����C�w���s�ɂ���ē������ʂ\�W������Ȃǂ��āA���̌�̊w�K�ɐ������悤�w������B
�������k�l���͑��݊Ԃ̐l�ԊW��s���ɂ��āA���s�̑O��̕ω����ώ@����R�̂Ȃ��悤�w������B
�A�Z��̌��N��ԁA���ɓ`���a�����̒���̗L���וK�v�ȑ[�u���u����Ȃnj��N�Ǘ��ɏ\�����ӂ���B
���s���ɕX�A���͂������O�ҁA��y�⏔�@�ւɑ��ė����o������悤�w������B